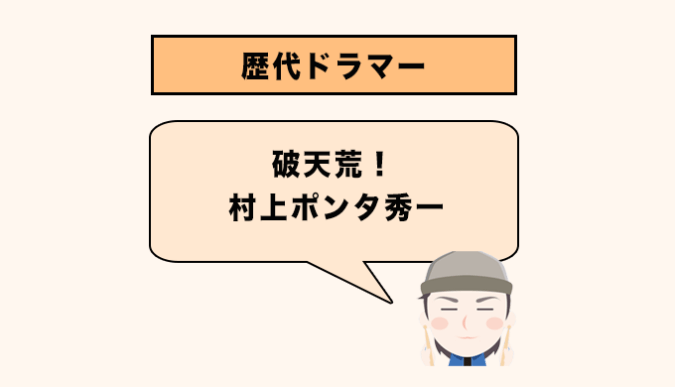Warning: Undefined array key 4 in /home/bassss/bremen-band.com/public_html/drum/lesson/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 21
Warning: Undefined array key 4 in /home/bassss/bremen-band.com/public_html/drum/lesson/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 33
Warning: Undefined array key 4 in /home/bassss/bremen-band.com/public_html/drum/lesson/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 21
Warning: Undefined array key 4 in /home/bassss/bremen-band.com/public_html/drum/lesson/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 33


誰もが認めるドラマー村上ポンタ秀一。
これまでサポートしたアーティストは、
- 椎名林檎
- 山下達郎
- 吉田美奈子
- 泉谷しげる
- 忌野清志郎
- 沢田研二
- 矢沢永吉
など多岐に渡って活躍されています。
しかし、ジャンルを超えて対応するのは至難の技で、誰でもできることではありません。
そこで今回は村上ポンタ秀一さんの
- プロフィール
- ドラム
- 伝説や小ネタ
などについて紹介します。
この記事を読んで村上ポンタ秀一さんの魅力が伝われば幸いです。

目次
村上ポンタ秀一のプロフィール

本名:村上秀一
生年月日:1951年1月1日生まれ(O型)
出身:兵庫県西宮市
バンド:セッションドラマー/スタジオミュージシャン
村上ポンタ秀一さんを一言で表すなら「破天荒」。
ズバッという性格で、賛否両論ある言動が目立つ、生粋のミュージシャンです。
一時は薬物で逮捕されてしまうこともありましたが、ポンタさん独特のグルーヴは唯一無二。

自伝も出版されておりますので、
村上ポンタさんの魅力を知りたい方は、一読されることをおすすめします。
略歴、バンド遍歴
ドラムを始めたキッカケ
ポンタさんがドラムを始めたのは中学生の時。
在籍していた吹奏楽部に指導に来ていた朝比奈隆にティンパニを勧められ、打楽器奏者の道を歩み始めます。
そして、21歳のときにバンド「赤い鳥」のオーディションを受け、合格。
そこから現在まで世界でも有数のプロドラマーとして活躍されています。

村上ポンタ秀一のドラムについて
ドラムセット
- PEARL
- スネア(メイン:Pearl/Reference Pure)
- スネア(サブ:Pearl/Olive Tree、Pearl/Ultracast Free Floating)
- シンバルはSABIANで統一
パフォーマンス
村上ポンタ秀一さんのドラムといえばキレのあるタイトなサウンドが印象的。
ドラムの音色一つ一つにすごく拘っており「アコースティックドラムの愛」を感じるほどです。

徹底した「ドラム愛」は職人のよう
数々のスタジオでラムを叩いてきた経験からドラムによって音の鳴りが違うことを認識してきた村上ポンタ秀一さん。
そのようなこともあって、音色にもこだわりがあるのですが某雑誌インタビューでこのようなことをおっしゃっていました。
「職人や仕事人だと思ってドラムをやりたいんだったら、まず”道具を知れ”」
アコースティック楽器はその時の気温や湿度によっても音色が左右されますから、ただ叩けば良い訳でな無いんですね。

amazon prime musicはPrime会員なら無料!お得に音楽を聴こう
amazon prime musicを使えば、200万曲以上を高音質&聴き放題!
Prime会員なら無料で利用できるので、一度お試しで使ってみてはいかがでしょうか?

ちなみに、prime会員の特典としては、
- 配送料無料
- お急ぎ便&日時指定無料
- Primeビデオで映画やドラマが見放題
- Prime Musicで音楽が聴き放題
- Prime Readingで無料で本を読める
- Primeラジオが聴ける
- Kindleが4000円引きで買える
- Kindle本が月1冊無料
と、かなりお得!
音楽だけでなく、映画も電子書籍も見れたり、amazonでの買い物送料が無料にもなりますよ。

また、下記記事で「Primeビデオで見れる音楽映画54作品」や「amazon musicの使い方&スマホへの保存方法」も紹介していますので、登録後に色々お試しください!
逸話や伝説、小ネタなど
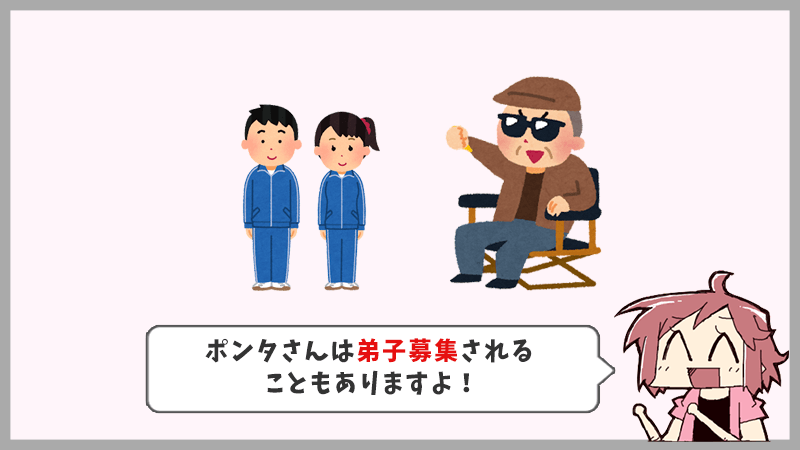
自身の著書「自暴自伝」で語る「スティーヴ・ガッド」の代役
ポンタさんの30周年に因んで、出版された自伝「自暴自伝」。
その中で「スティーヴ・ガッド」の代役をけっこう務めていたという話があります。
そういえば、ポンタさんのプレイはスティーヴ・ガッドのようなグルーヴ感を醸し出している印象がありますね。
セットも叩き方もそっくりだったらしく、一時期ポンタさんがNYに滞在している時にスティーヴ・ガッドの代役で叩いたことが何度もあったとのことです。
伝説のオーディション
ポンタさんが21歳の時。
以前より憧れていた「赤い鳥」のバンドにのオーディションを受け合格するのですが、この時のエピソードが強烈です。
オーディション当日28人志望者がいたが、8番目に受けた村上ポンタさんが受けた瞬間、即時でポンタさんの合格が決まり、9番目以降のオーディションが行われなかった
凄い伝説をお持ちですね!

ワイルドすぎる言動
村上ポンタ秀一さんは、かなりワイルドで物怖じしない発言が有名です。
某レコーディングの動画で、自分好みの音色じゃないドラムの音色に対して「これじゃあ音色、神保彰だよ」とコメントしている動画があります。
確かに、プレイが全然違いますが、凄い発言ですね。
村上ポンタ秀一さんと神保彰さんのプレイは確かに違いますが、2人はあまり仲が良くなかったのでしょうか?
一つ一つの音色に対して凄いこだわりを持ち、説得力のあるドラムを奏でるポンタさん。表現もとても繊細です。
ドラム弟子募集をすることも
村上ポンタ秀一さんは弟子募集をされることがあります。
昔はドラムマガジンでよく募集されていましたが、その時は「運転手兼ローディー」として募集されていたように思います。
プロミュージシャンの側で、ドラムのセッティングをしたり、ライブの裏側を見れるのは大きなチャンスでした。
現在は募集されているか分かりませんが、プロを目指している方は弟子募集にもアンテナを貼っておくのも良いですよ!

まとめ
村上ポンタ秀一さんについてまとめてきましたが、
- ワイルドかつ破天荒な性格
- 音色や道具を大事にする姿勢
と、複数の要素が合わさり、ポンタさんだけにしか叩けないドラムを構成されています。
ポンタさんのドラムは「歌うドラマー」とも称されることもあるので、是非一度「生音」を聞いてみてください!